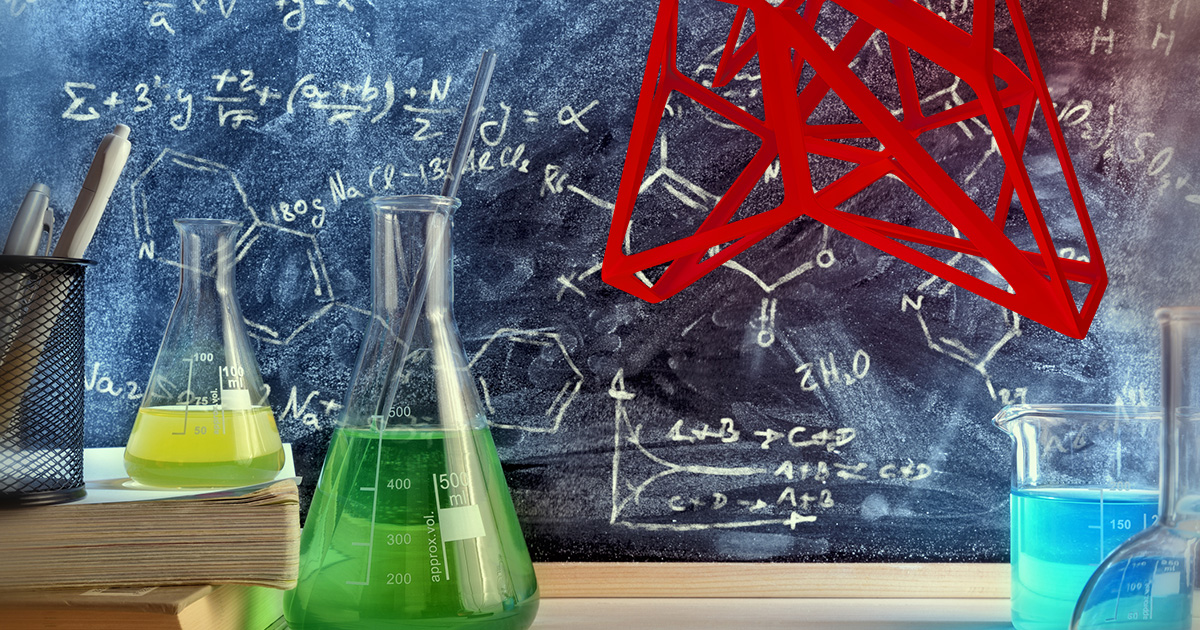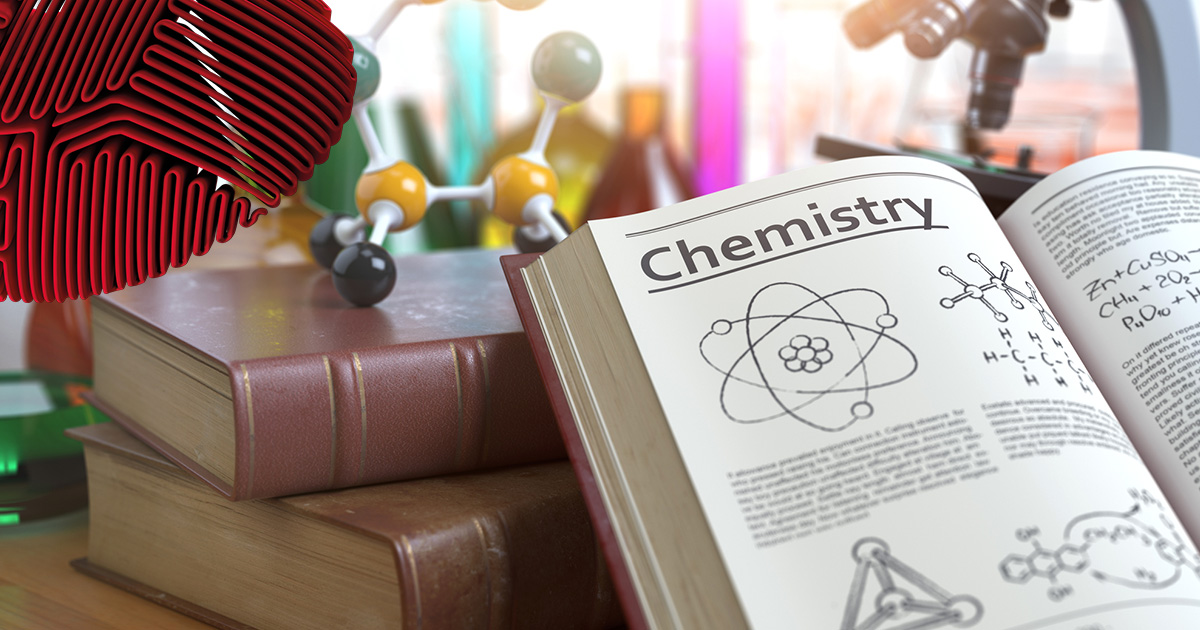<研究最前線>PETプローブの簡便作成を可能にした有機合成の技術
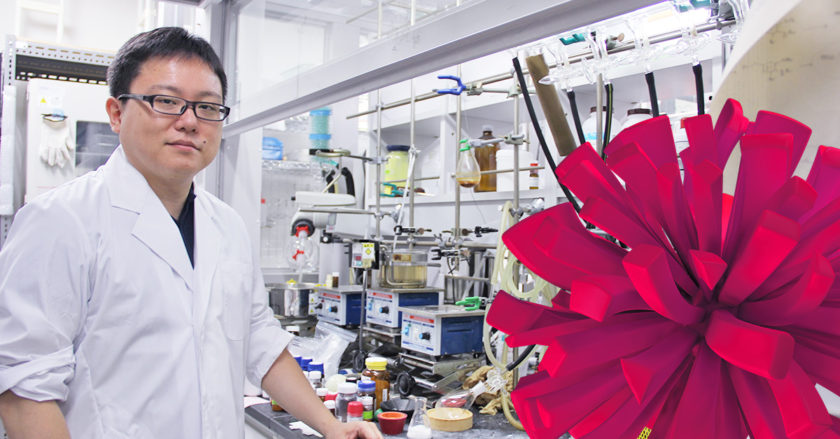
見たい分子をPETプローブに変えられる有機合成の技術とは
PETはポジトロン断層法(positron emission tomography)の略で、生体の機能を見る目的で医療や研究のさまざまな場面で使われています。陽電子を放出する放射性元素を含む分子を体内に投与することで、その分子の体内動態を撮影することができます。
たとえば、グルコースの2位の水酸基を、陽電子を放出するフッ素18で置換した「18F-FDG」を体内に注射し、しばらくしてから全身をPETで撮影すると、グルコースの代謝の様子がわかります。がん細胞は正常細胞に比べて3~8倍のグルコースを取り込む性質があるため、18F-FDGが多く集まっているところを見れば、がんの診断の手がかりになります。
このような、陽電子を放射してPETで撮影可能な分子を「PETプローブ」と呼びます。PETプローブには、18F-FDGのようにすでに確立されたものもありますが、様々な現象を見るためには見たい現象ごとに異なる分子のプローブが必要です。
この記事では、有機化学の手法を駆使して新たなPETプローブの開発に取り組んでいる理化学研究所生命機能科学研究センター分子標的化学研究チームの丹羽節副チームリーダーに、開発の苦労や工夫した点などを伺いました。
―PETプローブの合成が他の有機合成と違う点はどういうところですか?
一般的な有機合成の場合、ひとつの反応に何時間もかけても問題はないですが、PETプローブの場合は、放射性核種の半減期がありますから、合成は時間との戦いになります。よく使う「フッ素18」の半減期は109.8分しかありません。サイクロトロンでフッ素18を作る時間や、HPLCで分離して精製する時間を差し引いて、実際に使った時にゆっくりと撮影する時間を確保しようと思ったら、合成にかかる時間は1分でも短いほうがいいんです。
また、体内の動態を見るための分子の多くは、高温で加熱すると壊れたり性質が変わってしまったりします。ですから、できるだけマイルドな温度条件で合成することも必要になります。
さらに、PETプローブをせっかく開発しても、体内に投与してみるとあっという間に排出されてしまって使えなかったということもあるので、なるべく短い時間で開発や改良を繰り返せることも必要になります。
―これらの問題を解決するために開発されたのが「ホウ素化反応」ですね。
はい。ホウ素は反応性が高く、様々な原子や官能基に置き換えやすい原子です。「フッ素19」を陽電子を放射する「フッ素18」に直接置き換えるのは難しいですが、一度、フッ素19をホウ素に置き換えた前駆体を準備しておけば、ホウ素からフッ素18へは短時間で置換できるのです。
―開発において難しかった点はどういうところですか?
フッ素をホウ素に置き換える前に、フッ素を元の分子から切り落とさなくてはいけませんが、フッ素と炭素の結合は非常に強力で苦労しました。触媒としてニッケルと銅の2種類を同時に用いることで成功しました。
僕たちのモチベーションはPETプローブを作ることにあったので、この反応についてはあくまで手段として論文で述べたのですが、ジャーナルのレフリーにとってはここが面白かったようです。「炭素とフッ素の結合を切り落としたことを、なんでこんなに小さく書いているんだ。もっと大きく書け」と、書き直しを求められました(笑)
ホウ素に変えてしまえば応用は無限大
―この技術を応用すると、どのような可能性が広がりますか?
多くの薬にはフッ素が含まれています。そのため、薬の分子をフッ素18で標識できれば、薬が体内のどこに運ばれてどの程度の時間で排出されるかを見ることができます。新しい薬を開発したときに、人に飲んでもらって効果を見るのは莫大な費用と時間がかかりますが、PETを使えばごく少量で体内動態を確かめることができます。そうすれば、安全性の面でもコストの面でも大きなメリットになります。創薬のスピードがまったく違ってきます。
フッ素以外の原子も、一度ホウ素に置き換えることで新たなPETプローブを作れます。僕の所属する部署は2018年に3つのセンターが統合されて「生命機能科学研究センター」となりましたが、もともとここの建物は、PETイメージングの開発を目指して様々な分野の研究者が仕事ができるように作られました。
PETというのは、複数の分野の研究者が連携しあわないとできないんです。たとえば、放射性核種を作るサイクロトロンを扱う工学分野、分子プローブを合成する化学分野、そしてできあがったプローブを生体に入れて研究する生物学者や医師、さらに撮影した画像を解析する数学の専門家。これだけの人たちがそろってようやくできるわけです。僕は化学者ですから、生物学者の人たちが解決したい課題に合う分子をいつでも用意できるように準備しています。
―いったんホウ素化しておいて他の分子に置き換える技術はPETプローブ以外でどのような応用がありますか?
僕たちの研究室ではすでに多くの反応を開発していますが、代表的なものをふたつ挙げると、カルボン酸の変換とフルオロアルケンの簡便合成です。
カルボン酸はカルボキシ基をもつ有機化合物の総称です。生体内や薬剤や原料など、ありとあらゆるところで使われている分子なので、これを変換する技術が確立できれば、応用の幅が広がります。生命現象を分子レベルで追いかけるツールとして見たい分子に蛍光プローブをつけてみたり、材料科学の分野で、いい材料を作るために分子を変えてみたり、もちろん創薬にも応用可能です。
―フッ素をホウ素に置き換える技術を応用して、カルボキシ基の置き換えも可能になったわけですね。
いえ、実はそう単純な話ではなかったんです。カルボン酸とフッ素は全く違うので、炭素―フッ素結合を切るときに培った知見はほとんど役に立ちませんでした。
既存の方法だとカルボキシ基の結合を切断するには150℃以上の高温が必要だったのですが、それでは生体内分子には使えません。そこで、僕たちはまずカルボン酸と硫黄の化合物を反応させてチオエステルを合成し、炭素―硫黄の結合を切断してホウ素に置き換えるという方法を開発しました。80℃という比較的マイルドな温度条件で反応を行うことができました。
―もうひとつのフルオロアルケンの簡便合成の開発について、これはどのような応用が期待できますか?
フルオロアルケンというのは、生体内分子の基本骨格である「アミド結合」によく似ている分子です。似ているけれど、アミド結合と違って代謝安定性が高いという特徴があり、薬の構造として非常に注目されていました。またフルオロアルケンにはフッ素が入っているので、新たなPETプローブになる可能性もあります。
これまでは合成するのが難しくてあまり研究が進んでいなかったのですが、今回、フッ素が2つついているジフルオロアルケンに着目し、一方のフッ素だけにホウ素に置き換えることに成功しました。このホウ素が入った分子は、フルオロアルケンを合成するための材料に用いることができます。
このときは一度PETプローブから離れて純粋に反応や構造を研究していましたが、これが何の役に立つかということは常に視野に入れながら研究をしていました。単にフルオロアルケンができましたと発表するだけでなく、PETプローブの開発や創薬に応用できたりするということを言えるか言えないかは大きな違いだと思います。
応用と基礎を両方進めていくことが必要
―先生の研究は、応用を目指した目的志向の一面と、炭素―フッ素の結合をどうやって切るかというような知的好奇心を満たす純粋な基礎研究の面と、両方のバランスがとれていると感じましたが、そのあたりは意識されているのでしょうか。
両方をやっていくことが、研究者として身を立てていくひとつの方法だと思っています。化学の反応って、一度論文で発表してしまうと、誰でもできてしまうので、その技術を扱うときには、僕自身は必要ないわけですね。何か面白い技術を作りましたというだけでなく、自分だからこそ使える武器みたいなものを確立させたいと考えています。
また、PETプローブの開発はそれができる研究施設でないと行えないので、これだけをやっているとこの先の選択肢が狭まるだろうと考えています。PETプローブにもなるけれど、化学的な問題も解決する、そういう研究を目指しています。
さらに、化学的な問題だけでなく他の分野の問題も解決したいですね。他の研究分野には、化学で解決できそうな問題がごろごろ転がっているんです。それらを解決するためには、僕たちがしっかり化学をやっていかなくてはいけないと考えています。
―他の分野と連携することで有機化学の世界も広がっていくのですね!
そうです。たとえばPETプローブのように時間や温度の制約など開発面で大変な面もありますが、挑戦しがいがあります。PETプローブを開発したあとも、実際に実験に使ってもらうためには、生物学者が行う実験のスケジュールから逆算して合成を始める必要があるんです。合成し終わった試薬は鉛の容器に入れて急いで運びます。有機合成だけを行っているときとは違う緊張感があります。けれども、これをこなすことで初めて進む研究があるわけです。
―最後にM-hubの読者のみなさんにひとことお願いします。
若いうちに他の分野の人とも交流してみることをおすすめします。視野が広がって、自分の研究を違った視点から見ることができるようになると思います。
放射性分子を取り扱う実験施設で準備をする丹羽先生

プロフィール
丹羽 節(にわ たかし)
理化学研究所生命機能科学研究センター(BDR)分子標的化学研究チーム副チームリーダー
1981年生まれ。東京大学理学部化学科卒業、同大学大学院理学系研究科化学専攻修士課程修了、京都大学大学院工学研究科材料化学専攻博士後期課程修了。
日本学術振興会特別研究員およびアメリカ合衆国ハーバード大学化学・生物化学科博士研究員などを経て、2010年早稲田大学理工学術院先進理工学部化学・生命化学科 助教。2013年理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センター(CLST) 分子標的化学研究チーム 研究員、2016年同副チームリーダーを経て、2018年から現職。
同チームの最新論文はこちら
論文Pick up!
1. Ni/Cu-Catalyzed Defluoroborylation of Fluoroarenes for Diverse C–F Bond Functionalizations, Takashi Niwa et al., J. Am. Chem. Soc., 2015, 137 (45) :14313–14318
2. Rhodium-Catalyzed Decarbonylative Borylation of Aromatic Thioesters for Facile Diversification of Aromatic Carboxylic Acids, Hidenori Ochiai et al., Angew. Chem. int. Ed., 2017
3. Copper-Catalyzed Regioselective Monofluoroborylation of Polyfluoroalkenes en Route to Diverse Fluoroalkenes, Hironobu Sakaguchi et al., J. Am. Chem. Soc., 2017, 139 (36):12855–12862

下記フォームでは、M-hub(エムハブ)に対してのご意見、今後読んでみたい記事等のご要望を受け付けています。
メルクの各種キャンペーン、製品サポート、ご注文等に関するお問い合わせは下記リンク先にてお願いします。
*入力必須